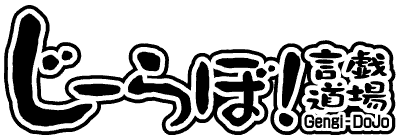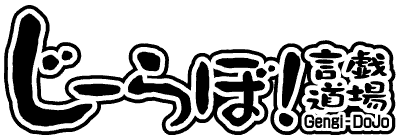|
■ 友達の友達の話[春九堂の場合#5:最終話 第3章]
「おっし、じゃあ今日はタックルの応用やっていきましょう」
準備体操を終えた直後のK先輩の快活な一言に、道場内は一瞬静まりかえった。
「応用…ッスか?」
後輩Mは、「不安」の二文字をオブラートに包み損ねた声でそう訊ねた。
「そう、こないだはバーピーやったりがぶったりで、タックル切ったらそこまでにしていただろ。今度は防御だけじゃなくて、タックル側としても切られても諦めないで、とにかく倒しに行くこと。そういう練習をしようというわけよ」
「なるほど…攻め手は倒すところまでですか?」
「いや、そこからフリーの寝技乱取りに持っていっちゃっていい。タックル受ける方も倒された場合は、とにかくグラウンドで相手をコントロールして極めさせないようにな。どっちかが極めるか、時間来たら交代ってことで」
「あ、そしたらマンツーマンですか?」
「そう。周りはしっかり攻め手と受け手に声かけて、指示出すこと。いいな」
「「「ぅいッス!」」」
つまりこういうことだ。タックルをする側と、受ける側で一人ずつ中央で向かい合う。合図と同時に攻め手側はタックルを狙う、受け手側はタックルをかわすべく努力する。完全にタックルが潰されたら、最初から。潰されなければとにかく倒しに行く。
また、そうでなく、受け手側が倒された場合は、そのまま寝技乱取りに入り、どちらかが関節技を極めるか、押さえ込むかしたら、最初から。そうでない場合は30秒ほどで「待て」をかけて、最初からになる。
残りの人は、受け手と攻め手がコンタクトをしたところから、攻める場所や攻め方を、よくよく観察して口頭で指示を出す。上の会話を説明すると、こういう練習をするということである。
あの後。そう、アクシデントで急所を打ってしまったH先輩を全員で押さえ込み、K先輩がアイスバックを急所に押しつけて、さらなるダメージを与えた、あの後。
H先輩は、終始無言に近い状態で、その日の練習を終えた。だが決して険悪なムードになったというわけではなく、冷たく濡れた道着の股間を気にしながらも、普通にその日は解散となったのである。
――表向きは。
それじゃはじめようか――K先輩の合図とともに、後輩MとSがまず中央に入り、攻防を繰り広げる。とはいうものの、2人ともタックルは門外漢。なかなかキレイな展開にはならず、揉みくちゃになっては戻される、そんな攻防が続く。
しかし何度も何度も行っていると、どうにか形にはなってきた。それにしてもとんでもなく疲れる練習だ。2人とも息が上がったところで、交代となる。
今度はK先輩とH先輩。K先輩は柔道の有段者でもあるので「双手刈り」というタックルの動きにもある程度馴れがある。対してH先輩は非常に軽いフットワークの持ち主で、そう易々とはきめさせず、ズバ抜けた反射神経でタックルを次々と潰す。
続いて後輩DとH先輩、SとK先輩、後輩Mと後輩Dというように、攻守を入れ替え何度も何度も繰り返しの練習を行った。
非常にキツい練習に、全員汗をダラダラとかいている。一端小休止となり、それぞれの動作について反省会をしていたのだが、そこでH先輩がダメ出しをした。
「ある程度慣れてきちゃうと、簡単に倒れて寝技に引き込もうとするだろ。それじゃダメなんだよ。あくまでも必死になってタックルを切ること。ここにいるのは基本的に全員タックルは門外漢だろ。本職のアマレス経験者とかは、タックルに来てから、倒すまでの技術もハンパじゃないわけだからさ、あくまでも倒れないことを前提にしなくっちゃ」
「「「ぅいッス!」」」
「そうだな。ちょっと必死さが足りないかも知れない。といっても俺ら全員かける側としても門外漢だからなぁ。さて、どうしたもんか」
「…うーん…」
全員考え込む。こうして方法を模索しながら練習を行うのも、この道場の自主トレメンバーの面白い点であった。楽しみながら強くなる。お互いの長所を引き出しあう。だからこその自主トレであったのだ。たとえ時々それが大幅に脱線する事があったとしても(例:映画「ベストキッド」のダニエルさんの片足立ち二段蹴りは本当に効くか)。
しばしの沈思黙考の後、H先輩が動いた。
「あ、そうだK」
「ん?どうしたよ」
「いやさ、こないだお前がもってきたアイシングバックあって、俺、九死に一生を得たじゃん」
どちらかというと、危うく男としての命を落としかけたような気がする。
「あ、ああ。うん。そうだな」
「お前、今日も持ってきてる?アイシングバッグ」
「応、持ってきてるぜ。氷も控え室の冷蔵庫に入れてある」
ニヤリ。
H先輩が太文字大書きでそういう効果文字を出すほど、邪悪に微笑んだのを、Sは見逃さなかった。
悪い予感が――
「そりゃいいや。それじゃアレ使おうぜ」
――的中した。
「実は俺も持ってきてるんだよ。2つあるならイロイロ出来るだろ」
――そして、予想を超えた。
1.アイシングバッグに氷を入れます。
2.利き手に軍手を装着します。
3.アイシングバッグを持ちます。
4.アイシングバッグをバンテージで軽く固定します。
5.構えます(この時アイシングバッグを持っている方が攻め手です)。
6.攻め手はタックルを仕掛けます。
7.受け手はタックルを切るべく努力します。
8.ガードが甘い場合、攻め手はアイシングバッグを押しつけます。
(このとき内股や股間を狙うと、大変効果的です)
9.押しつけられると、受け手は悶絶しながら嫌がり、防御を堅くします。
※よい子も悪ガキも精神年齢の若い大人も決して真似しないように!※
H先輩の考案した「特訓」は、上記のようなものであった。これが効果的な練習なのかはわからない。だが格闘技には「タックルや寝技をきらう」という言葉がある。これは「嫌う」というだけではなく、それを凌ぎきるという意味も表す。
タックルをがぶったならば、相手の利き手の逆方向に捌いてサイドからバック回り込む。バーピーで潰すならば、可能な限り下半身を遠くに伸ばしつつ潰す。つまり、相手の利き手のリーチ外から逃げる。これらは基本中の基本だ。

がぶり(青)

バーピー(青)
この「特訓」は、それには確かにうってつけだろう。汗をかいて湿っている道着の上からとはいえ(いや、だからこそなおさらに)アイシングバッグを押しつけられるなど、愉快なものではない。
それにそんなものを押しつけられれば確かに反射的に身を引く。押しつけられるのがイヤだから、アイシングバッグを持った相手の利き手が届く範囲から下半身(主にペニィ周辺)を逃すのだ。確かにいわれてみれば理に適ってはいるような気がする。
そんなH先輩のかなり怪しげな根拠解説に基づいて、この「特訓」は実施された。4割はH先輩に押し切られ、5割は全員の水遊びをする悪ガキのようなノリによって。
――そして残りの1割――それはおそらくH先輩の、あの「ニヤリ」――に、Sは漠然とした不安を感じていたのだった……。
<続く>
|
|